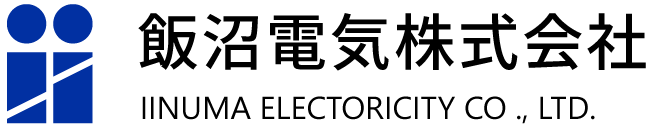碍子引き配線とは、昭和38年頃まで使われた配線方式です。白い陶器製の物が、配線の要である碍子と言われるものです。昔の配線は今のようにビニールで覆われているものはなく布製でした。
そのため配線の絶縁性をたかめるために、碍子で電線を壁から浮かして配線をしていたのです。
その後建築様式の変化や、電線の絶縁向上などで、次第に姿を消していった碍子引き配線ですが、近年では古民家風の住宅や店舗が注意され、それに伴うように装飾的に取り入れられています。
しかし、碍子を正しく扱える職人が非常に少なくなってきています。